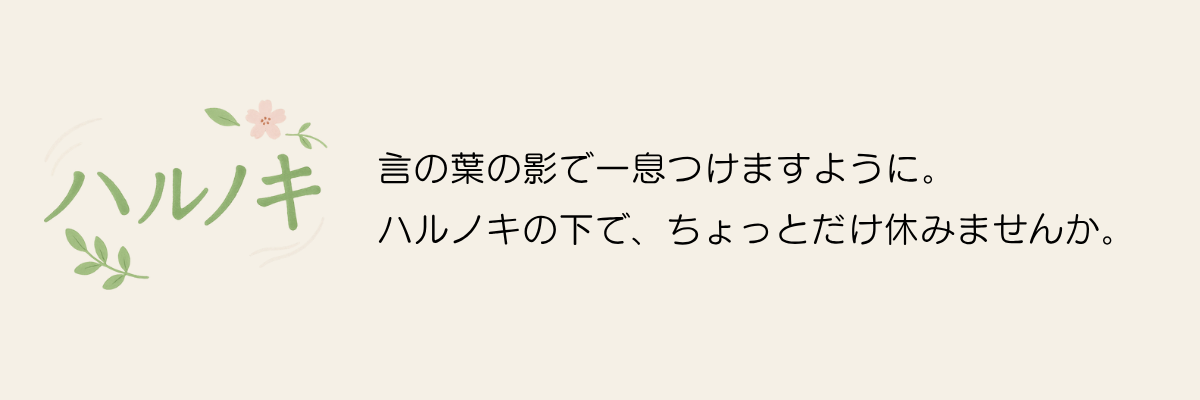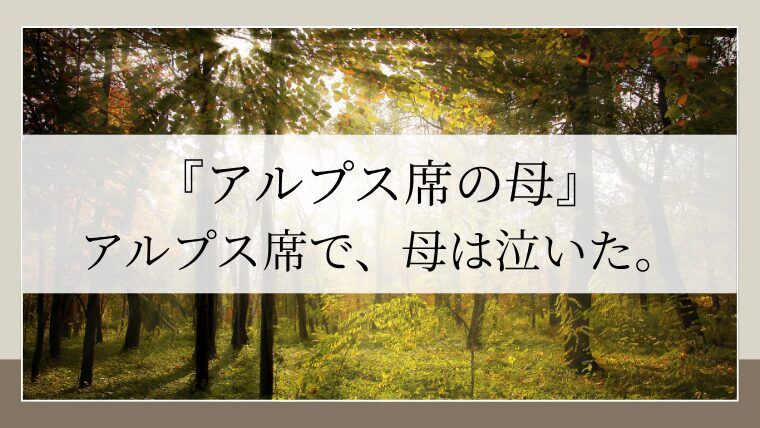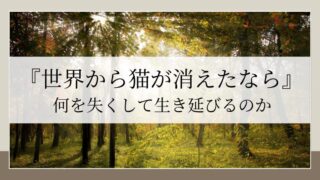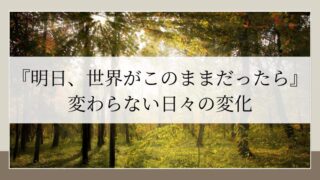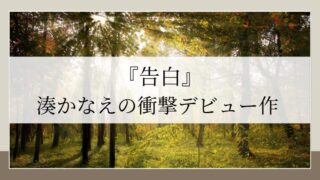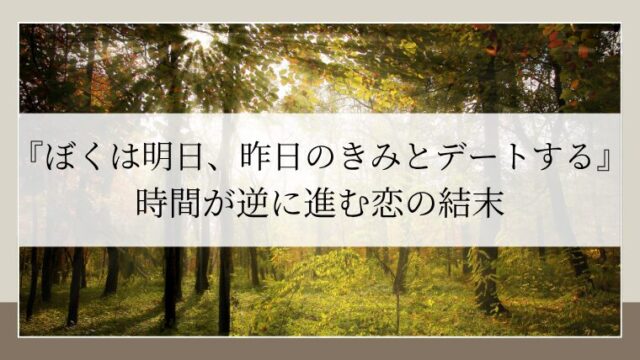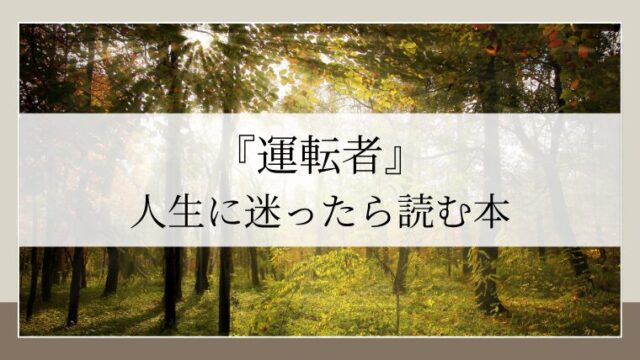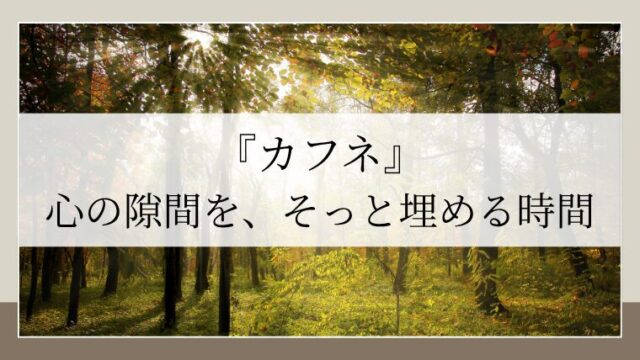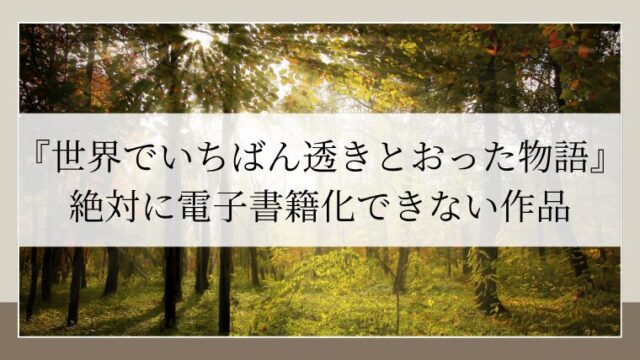目次
🌳『アルプス席の母』
甲子園を目指す息子を支える、ひとりの母の“応援席”での日々。
「子どもを支えたい」「でも自分はどうあるべきか」——そんな葛藤に揺れる小説『アルプス席の母』。
本記事では、あらすじ・感想・似たテーマのおすすめ本・読者タイプまで詳しく解説します(読了時間およそ5分)。
著者: 早見和真
出版社:小学館
刊行年:2024年3月

📖あらすじ
息子の夢は、甲子園出場。
その背中を支えるため、シングルマザーの菜々子は、息子とともに大阪の野球名門校へと引っ越す。
選手として成長していく息子を見守る一方で、菜々子は「母親としての応援」に戸惑いを抱く。
声を出すタイミング、横断幕の順番、監督への礼——そこには、母親同士の暗黙のルールがあった。
“全力で応援したい”という気持ちだけでは通じない空気が、確かに存在していた。
それでも、息子のひたむきな姿に心を動かされながら、菜々子は少しずつ、応援席という場所と向き合っていく。
息子の夢を見届けるために、母親として自分にできることを探しながら——。
甲子園を目指すのは、グラウンドの中だけじゃない。
母たちにとっての夏もまた、静かに始まっていた。
この本を読む前に知っておきたい5つのこと
- 本屋大賞 第2位(2025年)
2025年本屋大賞で第2位に選出された注目作。
「この作品こそ1位だ」と語る声も多く、読み終えた人の心に深く残る物語として高く評価されている。 - 母の目から見た高校野球
試合に出るのは息子。でも、母もまた別の場所で“甲子園”を目指していた。
息子を応援し続ける母の視点で描かれることで、これまでの高校野球小説とは一線を画す、もうひとつの青春が浮かび上がる。 - 応援席にも“戦い”がある
声の出し方、横断幕の順番、監督への礼……そこには応援にも厳然たる“ルール”が存在していた。
ただ全力で応援したいという気持ちが、空気や常識に押しつぶされそうになる場面も。
そのとき、自分だったらどうするのか、問いかけられるような読書体験になる。 - 部活の“美談”に隠れたひずみ
「頑張るのが正しい」「勝つことがすべて」——そんな空気に満ちた高校野球の世界。
母親たちの目線を通じて、誰もが一度は感じたことのある「違和感」が静かに描き出される。 - 「アルプス席の母」という言葉の重み
終盤、息子が語るあるひと言が、これまでのすべてを包み込み、タイトルの意味を鮮やかに浮かび上がらせる。
派手な感動ではなく、静かに胸を締めつけるような余韻が残る、忘れがたいラストが待っている。
🫶こんな人におすすめ
- 夢を追う誰かを、そっと支えたことがある人
応援する側の不安や迷いが、静かな言葉で丁寧に描かれていきます。 - 感情を抑えて頑張った経験がある人
何も言わずに耐えていたあの日の自分に、物語の中でふと重なる瞬間があります。 - “空気”に従うことに違和感を覚えたことがある人
応援席という場所に漂う見えないルール。
その中で揺れるひとりの母の姿が、心に沁みます。 - 家族を描いた物語が好きな人
親と子の距離、想い合い、すれ違い。
その関係性の変化が、リアルで切ない。 - 声にならない気持ちを抱えている人
誰かに話せなかった思いが、物語の中でそっと拾われていくような読後感があります。 - 静かに泣ける小説を探している人
感情を揺さぶりながらも、余韻の残るラストが、心をやさしく包み込みます。
📚この本が好きならこちらもおすすめ
『そして、バトンは渡された』瀬尾まいこ
【あなたには、いくつの“家族”がいますか?】
実の親、義理の親、血のつながらない親たち──
名字が何度も変わった少女・森宮優子は、家族を何度も“もらって”生きてきた。
自由すぎる継母、几帳面すぎる父。ひと癖ある大人たちと過ごす中で見えてきた、あたたかな日常。
そしてバトンのように、大切な想いは静かに受け継がれていく。
涙よりも、じんわり心に残る幸せをくれる、“家族のかたち”の物語。
きっとあなたも、自分の「家族」にそっと会いたくなる。
『昨夜のカレー 明日のパン』木皿泉
【もし、大切な人を失っても、日常が“そのまま”続いていくとしたら——】
夫を亡くして7年。テツコは義父・ギフとふたりで、今日も食卓を囲む。
思い出を話すでもなく、忘れるでもなく、ただ静かに日々を生きていく。
昨日のようなカレー、明日もきっと同じパン。
けれどその何気ない暮らしの中に、確かに“新しい時間”が流れ始めていた。
失ったものと、これからを生きる物語。
『アルプス席の母』を読んで ──はるのぽつり。
もし、応援しかできなかったとしても——
その“しか”が、誰かの心を支えていることがある。
この本を読みながら、ふと、自分の部活時代を思い出しました。
強豪校というほどではなかったけれど、それなりに勝ちを目指すチームに所属していた私。
でも、ずっと万年補欠でした。
試合に出られることは滅多になくて、
たまにチャンスが回ってきても、緊張で何もできずに終わってしまう。
そんな自分が、悔しくて、情けなくて、
「親に申し訳ない」とさえ思っていたことを覚えています。
それでも、親は毎週のように応援に来てくれていました。
早朝からお弁当を作って、重たい荷物を持って、
一度もベンチから立たない私の姿を、ずっと見つめてくれていた。
出番もなく、拍手されることもない私を、
どうしてあんなに優しい眼差しで見ていてくれたのだろう。
この小説のなかで、主人公の菜々子さんが
「応援席で戦う」という言葉に込めた想いは、
まさにあの頃の母や父の姿そのものでした。
選手が主役の物語ではなく、“応援する人”に焦点を当てたことで、
私はようやく、あのときの“応援”の意味を受け取れた気がします。
「出られなくてもいい」
「勝たなくてもいい」
——そんなふうに言いながら、
心のどこかでは、きっと、何かひとつでも報われる瞬間を願ってくれていたのだと思う。
涙が止まらなかったのは、物語のなかの母に、
そして、自分の親の姿が重なってしまったからでした。
“応援しかできなかった”のではなく、
“応援してくれていた”ということ。
それが、どれほどの力だったかを、
私はこの本でようやく気づくことができました。
ありがとう、って言いたくなった。
あの時の私に。
そして、あの時、見守ってくれていた人たちに。